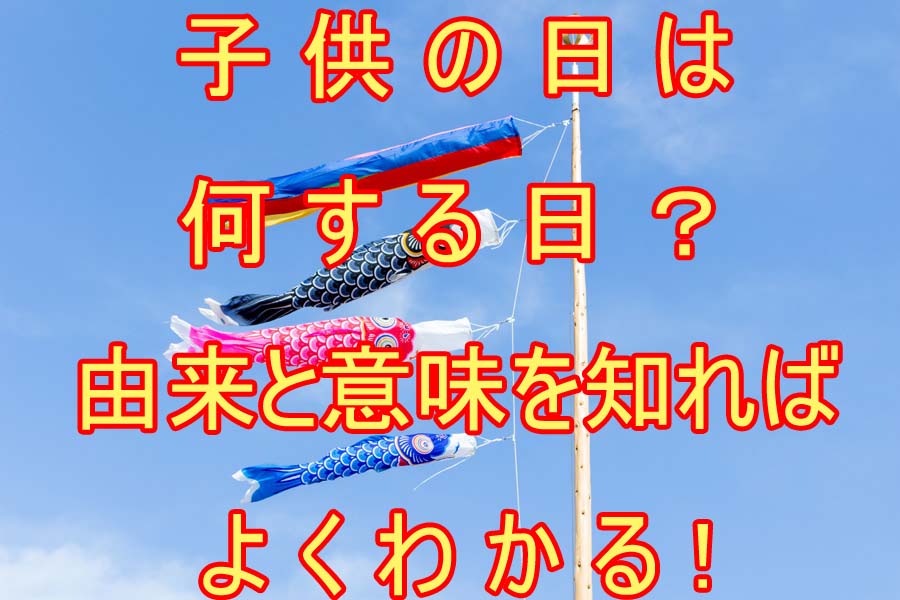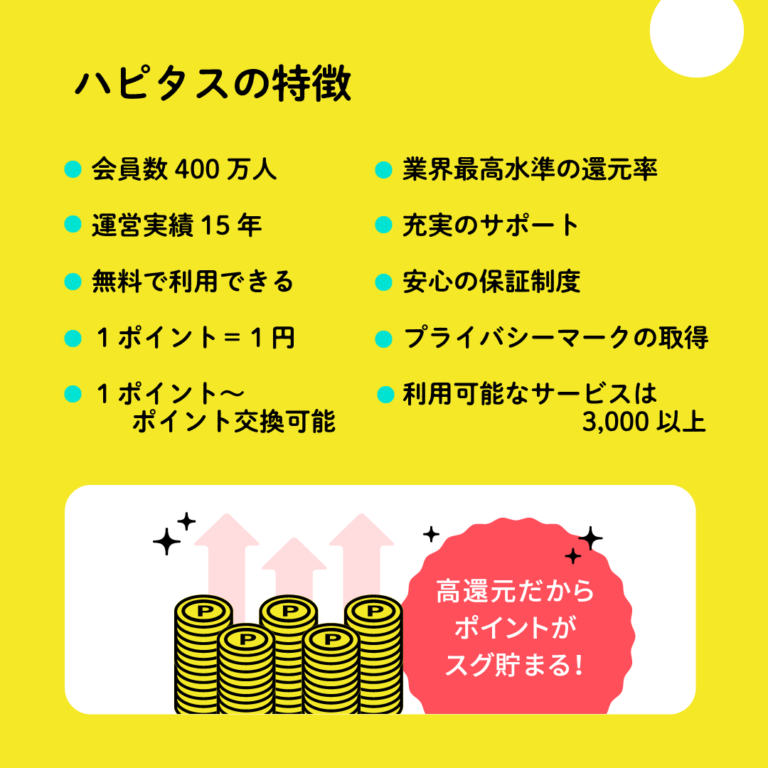[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] ・・・ただ、わたしにもなにかしてほしいな。
[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”] えっ?なんで?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] なんでって、こどもの日がどういう日か知らないの!
[/voice]
こどもの日というと、こどものための日と思いがちですが、実はそれだけではありません。
また、こどもの日は端午の節句ともいいますがなぜ言い方が2種類あるのかその違いをご紹介します。
こどもの日の由来と意味
端午(たんご)の節句ともいわれるこどもの日は5月5日となっており、祝日法で定める祝日の1つでありゴールデンウィークの1日も担っています。
なお、旧暦では5月は十二支のいうところの牛を司り、5月の最初の丑の日を節句として祝っていましたが、のちに5が重なる5月5日が端午の節句となりました。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] ちなみに、そのほかの節句としては3月3日の桃の節句が有名ですが、そのほかに7月7日の七夕、9月9日の菊の節句があるのよ。[/voice]
そして、祝日法ではこどもの日を「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日」ということとしています。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”] えっ!?こどもの日って子供の成長を祝うだけじゃなかったの!?こどもを産んだ母親にも感謝する日だったんだね[/voice]端午の節句の起源

さきほども解説しましたが、こどもの日である5月5日は端午の節句ですが、その起源は紀元前11世紀 – 紀元前223年に存在した楚(そ)の国にあります。
当時、楚には屈原(くつげん)という政治家がいましたが、敵対する組織の陰謀によって失脚し楚から追放されてしまいます。
屈原はその時の想いを「離騒(りそう)」と呼ばれる長編叙事詩につづり故国の行く末に失望し汨羅(べきら)という川に身を投げたとされています。
楚の国民たちは屈原の命日である5月5日に屈原の死体が魚に食べられないように、汨羅という川の船上で太鼓を打ってその音で魚を脅し、さらに肉粽(にくちまき)を投げ入れました。
そして、その風習は病気や厄除けとしての宮中行事になり、三国志でも馴染みのある魏(ぎ)の国により旧暦五月五日を端午の節句としてが定められました。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] 肉粽はもち米と一緒に竹の子や椎茸、豚肉を甘辛く煮つけ市、竹の皮で包んで蒸した料理で、日本でも馴染みのある”ちまき”はここが起源とも言われているわ。[/voice]
端午の節句は中国から日本に伝えられた
端午の節句が日本に伝えられたのは奈良時代頃とされています。
当時の日本でも、病気や厄除けの行事として行われており、「蓬(よもぎ)などの薬草摘み」「欄を入れた湯を浴びる」「菖蒲(しょうぶ)を浸した酒を飲む」という風習がありました。
端午の節句がこどもの日になるまで
日本も平安時代末期から武家政権へと移り変わるとともに、端午の節句の風習が廃れつつありました。
しかし、武士の間では尚武(しょうぶ)の気風が強く同じ発音の「菖蒲」とかけて、端午の節句を尚武の節句として祝うようになりました。
そして、江戸時代に徳川幕府が5月5日の端午の節句を重要な式日に定め、盛大にお祝いをするようになりました。
また、このとき将軍に男の子が生まれると、玄関前に馬印(うましるし)や幟(のぼり)を立てました。
そこから端午の節句は「五月人形」「こいのぼり」を飾り、男の子を祝う日になっていきました。
[/box]
こどもの日は何をする日なのか?
こどもの日の行事としては、中国から伝わる端午の節句にまつわるものと、日本で変化したこどもを祝う行事があります。
それらをご紹介します。
こいのぼりを飾る

マンション住まいの方も増えたので、飾るご家庭も少なくなりましたが、こどもの日にこいのぼりあげる風習があります。
これは、中国の故事である「鯉の滝登り」が揺らいで、こどもの出世を祈願するためにこいのぼりを上げます。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] 自宅に飾れない人はゴールデンウィークを利用して、杖立温泉(熊本)の鯉のぼり祭り、埼玉県加須市の平和祭り、仁淀川(高知県)の紙のこいのぼりなど有名なところにでかけるのもオススメよ。[/voice]
五月人形を飾る

こどもが生まれた初めて迎える端午の節句を初節句といい、五月人形や鎧兜をプレゼントする風習があります。
翌年からはそれらを飾るといいでしょう。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] 五月人形には鎧兜を羽織ったものや、金太郎、桃太郎のように物語の主人公をイメージしたものがあるのよ。これらは、こどもの人格を重んじ、幸福を祈るとともに、母親への感謝を表すのよ!
[/voice]
菖蒲湯に入る
こどもの日というより端午の節句として、日本で古くからある風習である菖蒲湯に浸かるのいいでしょう。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] 菖蒲湯に入るのは厄を払い健康に成長することを祈願するのよ![/voice] [box class=”glay_box” title=”菖蒲”] 葉の形状が刀に似ていることから中国では魔除けとして用いられていました。
日本にも中国から端午の節句と一緒に菖蒲も伝わり、日本全土に分布し、縁起物として扱われています。
菖蒲湯は、菖蒲の葉と球根を入れて沸かしたお風呂で、菖蒲湯に浸かると暑い夏を乗り越えられるとされています。
[/box]
ちまき・柏餅を食べる

端午の節句の起源である、中国で古くから伝わるちまきを作って食べてみてはいかがでしょうか。
また、日本では柏餅を食べるご家庭も多いのではないでしょうか。
実は、この柏餅は中国から伝わったものではなく日本が発祥の文化です。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”] 柏の葉には新しい葉が生えてくるまで古い葉が落ちないことから、子孫繁栄を祈願するものなのレシピ動画があるから参考にしてみてね[/voice] [arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=Anne6eD7Deg” mode=”normal” /]
まとめ
- こどもの日は中国が楚(そ)の時代に生まれた端午の節句が起源
- 端午の節句は中国が魏(ぎ)の時代に5月5日として定め、日本には奈良時代に伝わった
- 日本では奈良時代から平安時代末期までは端午の節句としての行事が行われていた
- 平安時代末期以降、端午の節句は男の子を祝う日へと変化していった
- こどもの日は「こいのぼり・五月人形を飾る」、「菖蒲湯に入る」、「ちまき・柏餅を食べる」といったことをする
こどもの日というと、こどものための日と思いがちですが、その母親への感謝をする日でもあります。
こどもの日はゴールデンウィークを構成する祝日の1つでもありますので、家族サービスをしてはどうでしょうか。