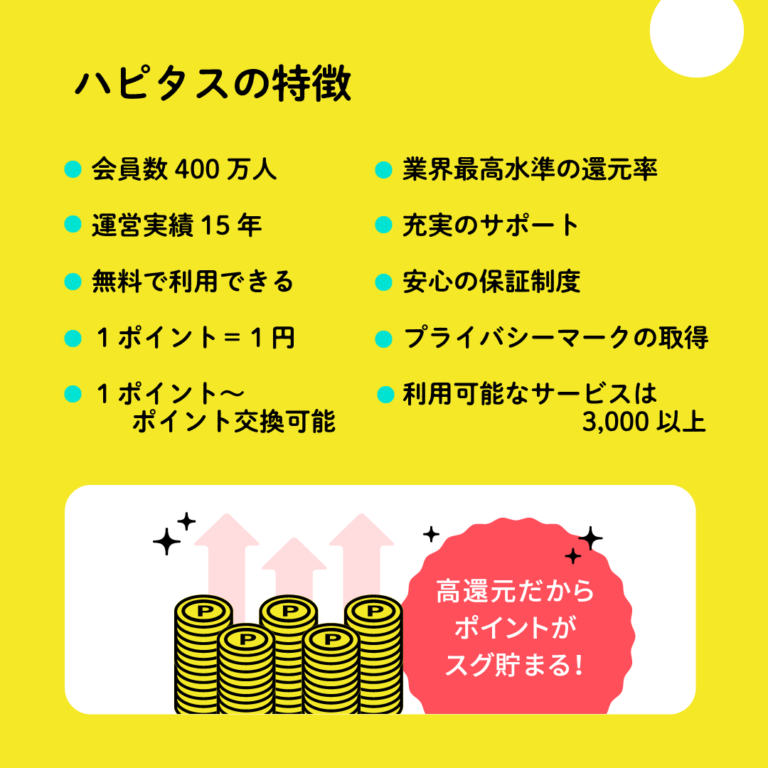夏が近づいてくると、だんだん食べたくなるのが、とうもろこし。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]一本丸ごと蒸したとうもろこしにかぶりつくのが何とも言えない幸せなのよね~♪[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]私の実家では、夏に家族みんな揃うと決まって、茹でたとうもろこしが食卓にドーンとだされて、みんなでわいわい食べてるよ。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-7.png” name=”かな” type=”r”]それは、すごく楽しそうな光景だね。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]うん。でも、とうもろこしってあまり日持ちしないから、余ったときやもらって帰って来たときの保存方法がわからなくて困ることがあるの。だから、今まで慌てて頑張って食べてたことあったな~。もう少し長く保存できるように何か方法はないかな?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]とうもろこしは冷凍保存ができるよ![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]えー!そうなの?知らなかった。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]じゃあ、保存の仕方を教えるね。[/voice]今回は、とうもろこしの便利な冷凍保存やお手軽なレシピについて紹介していきます。
知ってると便利なとうもろこしの冷凍保存方法
とうもろこしの旬は、6月~9月中旬です。
とうもろこしは、収穫した瞬間から糖度が落ちていってしまいます。
生のままでの保存では、新聞紙でくるんで冷蔵庫にきちんと立てて保存したとしても、3~4日しか持ちません。
しかし、冷凍保存をしておけば、だいたい1か月は保存することができます。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]へー!1か月も保存できるんだ。それは、すごい。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]それに、冷凍の仕方によっては、サクッと解凍できてちょっとした料理のアクセントにも役立つのよ。[/voice]とうもろこしは、生のままでも火を通した後でも、冷凍することができます。どちらも基本的には、保存の仕方は一緒です。
[box class=”pink_box” title=”冷凍保存の方法”](生のままあるいは、火を通した後)・とうもろこしをいくつかの輪切りにしてから、ラップでしっかりとくるんでから、ジップロックに入れて冷凍。
・とうもろこしの実をバラバラにしてからジップロックに入れて冷凍。[/box]
状態にもよりますが、火を通したものに比べると、生のままのものの方が多少劣化が早いので、火を通してからの冷凍をおすすめします。
火を通してから冷凍する場合、通常よりも少し固めに茹でて冷凍した方が、いいです。
また、茹でた直後は、とうもろこしの水分が抜けやすく、しわしわになってしまうので、手早くラップに包みましょう。
[arve url=”https://youtu.be/5TQfR0NAxvk” mode=”normal” /]
[arve url=”https://youtu.be/umELHRTRR4E” mode=”normal” /]
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]ひと手間かかるけど、とうもろこしの実をバラバラにした方がサラダにパラパラっとかけたり、サッと炒め物に入れたりできるから便利。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]私ずぼら主婦だから、正直そういうのめんどくさいな~(笑)とうもろこしの粒が取れるような便利なグッズはないかな?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]それなら、これはどうかな。[/voice]
とうもろこしの実をバラバラにするためのグッズ
ツインハンドルコーンカッター
これは、とうもろこしの芯に合わせて真ん中の穴を通して両手で押して粒をそぎ取るためのものです。
簡単に粒を一気に取ることができますが、とうもろこしによっては、サイズが合わない可能性もあります。
とうもろこしピーラー
とうもろこしの粒を一列ずつそぎ取るためのものです。
あまり力もいらず。比較的綺麗に粒を取ることができます。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”r”]こんな便利なものがあるなんてびっくり!これなら、私でもできそう。[/voice]
とうもろこしの茹で方
とうもろこしを食べるためには茹でなければなりませんね!
茹で方を2種類、ご紹介します♪
鍋での調理の仕方
一般的には、とうもろこしを茹でるときには、鍋に塩とお水を入れて沸騰させた中にとうもろこしを投入して10~12分ほど茹でると思います。
が、実は、水から茹でる場合とお湯から茹でる場合とでは、茹であがりの実の触感などが変わってきます。
美味しくとうもろこしを食べるための茹で方を紹介します。
[box class=”pink_box” title=”お湯から茹でる場合”]1.まずは、塩を加えずに水を入れた鍋を火にかけ、沸騰させます。
2.とうもろこしを入れ、5分茹でる。
3.落し蓋をする。なければ、とうもろこしを箸などでくるくる回しながら茹でる。
4.濃い塩水に10分漬ける。
果肉の食感がシャキッとした仕上がりになる。天ぷらや炒め物におすすめ。
[/box][box class=”pink_box” title=”水から茹でる場合”]
1.水を入れた鍋に、とうもろこしを入れ火にかける。
2.落とし蓋をする。なければ、とうもろこしを箸などでくるくる回しながら加熱。
3.沸騰してから、5分茹でる。
4.引き続き、落とし蓋をする。なければ、とうもろこしを箸などでくるくる回しながら加熱。
5.濃い塩水に10分漬ける。
果肉がふっくらジューシーになる。サラダなどにするのがおすすめ。
[/box]※濃い塩水…水1リットルに対して、30グラムの塩を入れたもの。
参考 旬の食材百貨
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]水から茹でるのとお湯から茹でるのでは、違いがあるんだ。好みの食感を探して、作りたいものによって茹で方を変えてみるのもいいね。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]後から、塩水に漬け込むことによって、実に塩水が染み込むし、実がしわしわになってしまうのを防ぐことが出来るのよ。[/voice]電子レンジでの調理の仕方
外皮がある場合は、皮ごとそのままレンジに入れます。外皮がラップの役割になるので、ラップはいりません。500Wでだいたい5~6分程度加熱して出来上がり。
外皮がない場合は、ラップで包みましょう。
[arve url=”https://youtu.be/SWf_hv1hDIU” mode=”normal” /]
解凍方法
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]茹で方、冷凍の仕方が分かったから、今度は解凍の仕方だね。[/voice]生のまま冷凍してある場合
- 鍋に水ととうもろこしを入れ、水の状態から火にかけ茹でる。
- 新しいラップでふんわりと包み、電子レンジで7分(500Wの場合)温める。
火を通した後に冷凍した場合
- 一番美味しく食べられるように解凍する方法は、前日のうちから冷蔵庫移して、ゆっくり解凍させる方法。この方が、水分を残したまま解凍できるのでみずみずしいとうもろこしが食べらます。
- 時間がない場合は、電子レンジの解凍機能を使いましょう。
- ばらばらの状態で冷凍してある場合は、冷凍庫から取り出してそのまま炒め物などに使用しても大丈夫です。
解凍したとうもろこしで簡単料理
とうもろこしを使って、ササっとできる簡単レシピを紹介します。

![]() 韓国料理❀コーンとチーズのおやつチヂミ by gogelhopf
韓国料理❀コーンとチーズのおやつチヂミ by gogelhopf


[the_ad id=”11303″]
とうもろこしの栄養
日本でとうもろこしは、おやつに食べたり、おかずレシピに使ったりしますが、世界の中では、米や小麦のように、主食として食べている国もあります。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]そいえば、私の姉の子が全然米を食べてくれなくて、とうもろこしは好きでとうもろこしばっかり食べてた時期があって、小児科の先生に相談したことがあったんだ。でも、外国ではとうもろこしを主食として食べてるところもあるからそんなに心配いらないよ。って言われてほっとしたって言ってたな~[/voice]
そして、食物繊維が豊富で、便秘解消を促します。ビタミン・ミネラル・鉄分も豊富で、コレステロール値を下げる働きをするリノール酸や体液バランスを整えるアミノ酸なども含まれています。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]こうやってみると、とうもろこしって体にいいことばかりなんだね![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]そうだね。でも、とうもろこしには、糖分も含まれているから、大人は食べ過ぎると太ってしまうから注意してね(笑)[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]そっか~なんでも、ほどほどがいいんだね(笑)[/voice]
とうもろこしの選び方
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]とうもろこしって、スーパーなどで売られてるとき、葉っぱに覆われてて中身を確認できなでしょ?たまに買って帰ってきて、むいてみたらガタガタで実が少ないようなものだったりしてがっかりすることがあるの。葉っぱを全部むいて確認することはできないし…[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]それは、せっかく買ってきてもがっかりするわね。とうもろこしを選ぶ基準があるから、それを覚えとくといいよ。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]それは、ぜひ知りたい!![/voice]とうもろこしは、大きく分けて5つの種類に分類されます。
- スイートコーン(甘味種)…普段食べているとうもろこし
- ポップコーン(爆裂種)…ポップコーンを作る
- デントコーン(馬歯種)…コーンスターチの原料
- ワキシーコーン(もち種)…もち米のような食感
- ソフトコーン(軟粒種)…実が砕けやすく、断面が粉状になりやすい
この中で普段私たちが食べているとうもろこしは、スイートコーンです。そして、スイートコーンは三つの種類にわかれます。
- ゴールデンコーン(黄粒種)…ゴールドラッシュ、味来など
- シルバーコーン(白粒種)…ピュアホワイト、ホワイトレディなど
- バイカラーコーン(バイカラー種)…甘々娘、ゆめのコーンなど
スーパーなどで売られているのは、バイカラーコーンのものが多いです。
同じ品種のとうもろこしでも、より美味しいとうもろこしを選ぶためにポイントを抑えておきましょう。

- 外皮(葉っぱ)の緑が濃いものを選ぶ。
- ひげは、茶色いものを選ぶ。
- ひげの本数が多いものを選ぶ。
- もし、中身が少し見えるのであれば、粒の大きさや、綺麗に粒が並んでいるかみる。[/box]
外皮が綺麗な濃い緑色だと、光合成をきちんと行っている証拠なので、美味しいです。そして、劣化が進むにつれて、緑色も薄くなって行くので濃いものは、より新鮮な可能性が高いです。
ひげは、なんとなくきれいな緑色を選びがちですが、茶色くなっているものの方が、熟成されている証拠なのです。ひげの一本一本が実につながっていると言われているので、ひげが多いほうが実が詰まっています。
とうもろこしを持って外皮の上から軽く握ってみて、実が詰まっているか確認するのもいいかもしれません。ですが、売り物ですので、実をつぶさないように気をつけましょう。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]とうもろこしを外からみるだけで、こんなに選ぶポイントがあったなんて!今度、買うときしっかり見てみるわ。[/voice]
まとめ
- 冷凍保存期間は1ヶ月。
- 冷凍するなら生のままより火を通した方がおすすめ。
- 通常よりも少し固めに茹でて冷凍する。
- バラバラにして冷凍しておくと楽。
- 解凍後ちょっとした料理に使えて便利。
すぐに食べきれなくて余ってしまいそうなとうもろこし。上手に冷凍保存して、プラス一品のおかずやおやつなどに利用してみて下さい。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/女性社員ほほえみ.png” name=”あい” type=”l”]とうもろこしは冷凍保存しておくと、とても便利なことが分かったわ。今年の夏、さっそく試してみよう![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]不足しがちな食物繊維とかもサッと解凍して料理に入れれば気軽にとれるからとってもいいわね。私もツインハンドルカッターとか買ってみようかな♪[/voice][box class=”pink_box” title=”関連記事まとめ”]