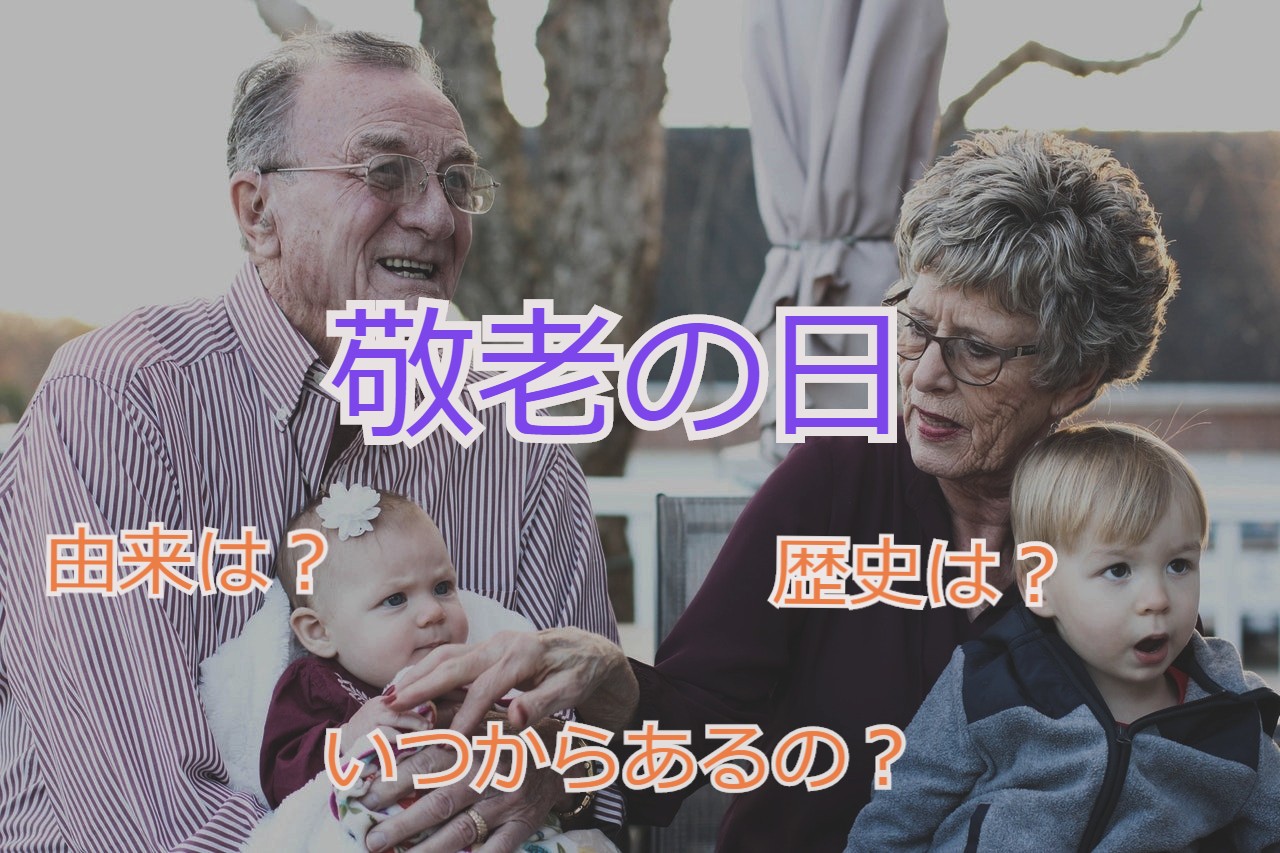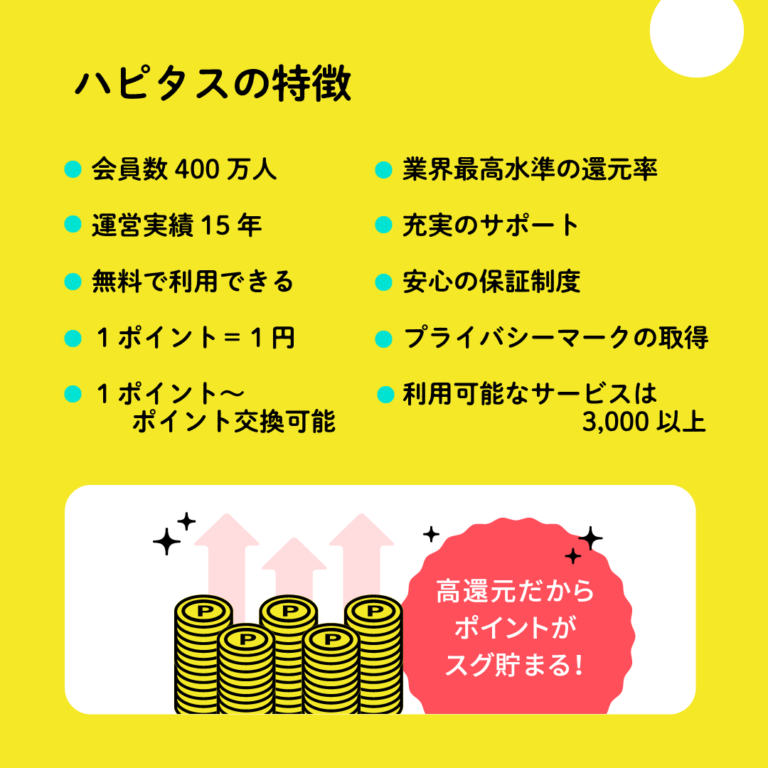敬老の日といえば、お年寄りを敬いその気持ちや感謝を伝える日。
核家族化が進む現代では、離れて住む自分のおじいちゃんおばあちゃんにプレゼントを贈ったり、老人ホームでの交流やイベントなどの催しが主流となっています。
今回はそんな敬老の日がいつどこで生まれ、どんな経緯で国民の祝日となったのかを調べまとめてみました。
敬老の日の由来
敬老の日は国民の祝日であり、学校や一般企業などがお休みとなるのは常識ですよね。
そんな敬老の日が国民の祝日となるまでには、ある人物が長い道のりをかけて尽力した背景があるのです。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”r”]僕は休日を作ってくれた人には積極的に感謝の気持ちを表したいな![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]そ、そうよね(お年寄りへの感謝はどこへ・・・)[/voice]敬老の日発祥の地
兵庫県多可町にある八千代コミュニティプラザに、「敬老の日提唱の地」と書かれた石碑があります。

これは町のシンボルであり町民の誇りであるそうです。
多可町では敬老の精神をいつまでも受け継いでいこうという思いで、毎年「喜寿敬老会」や「おじいちゃんおばあちゃん児童画展」などを開催。
さらに平成25年には公募で「きっとありがとう」という敬老の歌を制作しています。
敬老の日のはじまり
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]敬老の日発祥の地はわかったけど、この地でいつどのように敬老の日ができたの?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]門脇政夫さんという村長さんが、1947年(昭和22年)に開催した敬老会がはじまりと言われているそうよ[/voice] [box class=”pink_box” title=”門脇政夫”]1911年(明治44年)生まれ。1947年に35歳で兵庫県多可郡野間谷村(現・多可町八千代区)の村長に当選。
その後1967年(昭和42年)から1979年(昭和54年)まで兵庫県会議員を務める。
2010年(平成22年)98歳で急性呼吸不全により亡くなる。
[/box]「長年社会に貢献してきたお年寄りに敬意を表し、より良い村づくりのためにその知識や経験を次の世代に伝授してもらう場を設けよう。」
そう考えた門脇氏は、当選した年の9月15日に村主催の敬老会を開催。
55歳以上の村民を公会堂に招待し、食事と余興でもてなしたそうです。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]55歳って、今では現役バリバリの年齢だよね!?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]今では60代や70代でも元気な方が多いものね[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]それに1947年てことは、意外と最近なんだね。もっとずっと昔の、江戸時代ぐらいからの風習だと思ってたよ。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]そうなのよね。提唱者の門脇さんも数年前までご存命だったのよ。[/voice]訃報:門脇政夫さん98歳=「敬老の日」提唱者 http://bit.ly/bHmHrt
— 毎日新聞ニュース (@mainichijpnews) February 20, 2010
当時日本は戦後の混乱が続き、子供を戦地に送った親御さんたちは精神的に疲れ切っていたと、門脇氏は語っています。敬老会はそんな方たちへ報いるために催され、それがきっかけで後の敬老の日が誕生したというわけですね。
敬老の日の歴史
門脇氏の熱い思いで開催された敬老会。
その後敬老会はどのようにして現在の敬老の日になったのでしょうか。
[box class=”glay_box” title=”敬老の日ができるまで”]- 1947年(昭和22年)9月15日・・・第一回敬老会開催
- 1948年(昭和23年)7月 ・・・「国民の祝日に関する法律」制定
この「国民の祝日に関する法律」には子供の日・成人の日は定められたが、敬老の日(老人のための祝日)はどこにも定められなかった。
- 1948年(昭和23年)9月15日・・・第二回敬老会にて、「としよりの日」として9月15日を村独自の祝日とすることを提唱
門脇氏の働きかけにより、県内の市町村でもその趣旨への賛同が広がった。
- 1950年(昭和25年)・・・兵庫県が「としよりの日」を制定。県内全域で敬老会を開催。
- 1951年(昭和26年)・・・中央社会福祉協議会(現・全国福祉協議会)が「としよりの日」(9月15日)、運動週間(9月15日~9月21日)を定めた。
次第に「としより」という表現に批判が集まる。
- 1963年(昭和38年)・・・老人福祉法が制定される。「としよりの日」は「老人の日」へ、1週間の運動週間は「老人週間」と名称が変更される。
- 1964年(昭和39年)・・・老人福祉法の実施。
- 1966年(昭和41年)・・・国民の祝日に関する法律が改正され、9月15日を「敬老の日」として国民の祝日に制定。それとともに老人福祉法の「老人の日」も「敬老の日」に改められる。
初めて敬老会が開催されてから全国的に「としよりの日」が制定されるまでわずか4年。
門脇氏の行動力と、人生の先輩方に対する大きな尊敬の念が感じられますね。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]9月15日ってちょうど年度の真ん中って感じがするけど、何か理由があるのかな?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]じゃあ次は敬老の日が9月15日である理由を調べてみましょ![/voice]敬老の日が9月15日である理由
初めて敬老会が開かれたのが9月15日であり、それを元に後の「としよりの日」や「敬老の日」が9月15日となったのは想像できます。
ではなぜ9月15日なのでしょうか?
農閑期

提唱者の門脇氏によりますと、9月中旬は気候も良く、農閑期であるため時間に余裕があったことが、9月15日に敬老会を開催した理由とのことです。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]のうかんき?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]農業の仕事が暇になる時期のことよ。確かに仕事が忙しくない時期の方が、敬老会にご招待しやすいかもね。[/voice]養老の滝伝説
また門脇氏は「養老の滝の伝説にヒントを得た」とも語っています。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]養老の滝って、あの居酒屋の?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-8.png” name=”かな” type=”l”]違うに決まってるでしょ![/voice] [box class=”pink_box” title=”養老の滝伝説”]昔々、美濃の国(岐阜県)に、大変親孝行な若者がいました。
若者は年老いた父親と二人暮らしで、山で薪を取ってそれを売り生活していましたが、毎日食べるものにも困るほど貧しい暮らしでした。
ある日若者がいつものように山へ入ると、足を滑らせて谷底へ転がり落ちてしまいました。
そこには滝が流れ、喉が渇いていた若者は手ですくってその水を飲んでみました。
するとそれはなんとも香しく美味しいお酒ではありませんか。若者は瓢箪(ひょうたん)にその酒を汲んで、大の酒好きである父親のために持って帰りました。
その酒を飲んだ父親は一口飲んでは美味いと驚き、みるみるうちに体の不調が取れ若返っていきました。
この話は都の天皇にも伝わり、大変感心し若者に山ほどの褒美を授けました。
天皇は実際にこの滝を訪れ水を飲み「養老の滝」と名付け、さらには年号を「養老」としたのでした。[/box]
この伝説で、天皇が滝を訪れたのが9月だったというのが、敬老会を9月15日に開催した理由のひとつとなったそうです。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性うれしい.png” name=”夫” type=”r”]ほら、やっぱり酒じゃないか!居酒屋というのも間違ってないよね?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]た、たしかに・・・[/voice] [aside]余談ですが・・・居酒屋チェーンの「養老乃瀧」も、この養老の滝の伝説を由来としているようです[/aside]
悲田院建立の日
悲田院とは貧しい病人や孤児、身寄りのない老人などを救うために建てられた施設。
現在の老人ホームのような施設です。
その悲田院が建立されたのが9月15日といわれており、それを参考にしたとする説もあります。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]現実的な由来としては、初めて敬老会が開かれた日。でも養老の滝の伝説や悲田院建立に由来するというのもロマンがあるね[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]長年9月15日に定着していた敬老の日だけど、平成になってから日にちが変わったのよね[/voice][the_ad id=”11303″]
ハッピーマンデー制度の影響

2001年に制定された、いわゆる「ハッピーマンデー制度」
成人の日や体の育日などと共に、それまで毎年決まった日にちに祝日として定められていたものが「〇月の第〇月曜日」となったのです。
これによって土・日・月と三連休となり、国民に余暇を過ごしてもらおうという制度なのですが・・・
敬老の日の提唱者である門脇氏は、ハッピーマンデー制度によって敬老の日の日にちが変わることに対しては反対だったようです。
門脇氏だけでなく、複数の高齢者団体がこれに反対。
それを受けて2001年(平成13年)に老人福祉法が改正され、それまで敬老の日であった9月15日を「老人の日」、それから1週間を「老人週間」と定め直すことになりました。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]門脇さんはこれまで敬老の日制定に尽力してきたこともあるし、9月15日という日付に一層の思い入れがあったのかもしれないわね。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”l”]でも老人の日と老人週間って、敬老の日と何か違うのかな?[/voice]「敬老の日」と「老人の日」「老人週間」
敬老の日の趣旨は、国民の祝日に関する法律第二条によって次のように定められています。
[box class=”yellow_box” title=””]多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う[/box]それに対し、老人の日・老人週間の目的について定めているのは老人福祉法第一章第五条。
[box class=”yellow_box” title=””]国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促す[/box]定められている法律と、趣旨や目的も少し違いますね。
敬老の日は単純にお年寄りを敬う気持ちと長寿のお祝いをしようという日。
老人の日と老人週間は、老人福祉への啓蒙・啓発に加え、お年寄り自身にも向上心を持ちましょうと呼びかけています。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/30代男性普通.png” name=”夫” type=”r”]老人の日や老人週間って、高齢化社会が進む現代にはとても重要なことだよね[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]もちろん子どもの福祉も大事だけど、高齢者が生き生きとしている社会には未来に希望が持てるものね[/voice]世界の敬老の日
敬老の日はその歴史や由来から見ても日本特有の祝日ですが、海外にもお年寄りを敬い感謝する日はあるのでしょうか。
アメリカ「祖父母の日」
アメリカでは9月の第2日曜日を「祖父母の日」としています。
孫から祖父母へ、グリーティングカードに勿忘草(わすれなぐさ)を添えて贈るようです。
日本の敬老の日でもできそうですね♪
イギリス「女王陛下からの祝電」
イギリスでは暦に定められた祝日などはありませんが、100歳と105歳の誕生日、そしてそれ以降の誕生日には毎年女王陛下から祝電をもらうことができるようです。(※要申請)
昨日は車で片道4時間、ロンドン郊外まで、昔うちの近所に住んでいたお婆さんの100歳の誕生日会に行って来ました。写真はエリザベス女王からのお祝いのカード。イギリス人は100歳の誕生日に女王様からカードがもらえます。タイタニック号が沈んで4年後に生まれたってことよね。すごっつ! pic.twitter.com/Dao0plFTEb
— clever yummy (@cleveryummy) November 28, 2016
韓国 誰も知らない「老人の日」
韓国では10月2日を「老人の日」、10月を「敬老の月」としているのですが、知名度が低くその存在をほとんどの人が知らないそうです。
一見薄情なように思えますが、韓国では儒教の精神で年長者を敬うことは当たり前とされていて、毎日が敬老の日のような気持ちでいるとのことです。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]なるほど、考えさせられる意見ね[/voice]まとめ
いかがでしたか?
敬老の日の提唱者が最近までご存命だったことや、9月15日が老人の日となっていたことに驚かれたのではないでしょうか。
敬老の日や老人の日に限らず、年長者を敬う気持ちと感謝の心は忘れずにいたいですね。
それでは敬老の日についてのまとめです!
[box class=”yellow_box” title=”敬老の日の由来”]- 門脇政夫という兵庫県の村長が敬老会を開いたことが始まり
- 敬老の日が祝日になるには長い道のりがあった
- 9月15日というのは「養老の滝伝説」「悲田院建立の日」が由来という説がある
- ハッピーマンデー制度施工後9月15日は老人の日、その後1週間は老人週間となった
祝日はただ単にお休みで嬉しいだけのものと思いがちですが、その意味や制定までの過程を思うと、その日の過ごし方も変わってきそうですね。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]パパとママがお年寄りになったら、ちゃんと敬老の日をお祝いしてあげるから安心してね[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/nigaoemaker-2.png” name=”夫” type=”l”](その頃までに嫌われてないといいなぁ・・・)[/voice] [box class=”glay_box” title=”関連記事”]敬老の日のプレゼントのオススメは?孫からの手作りに感動!手紙に涙!
シルバーウィークとは?毎年あるの?その起源と由来はなに?いつから?
[/box]