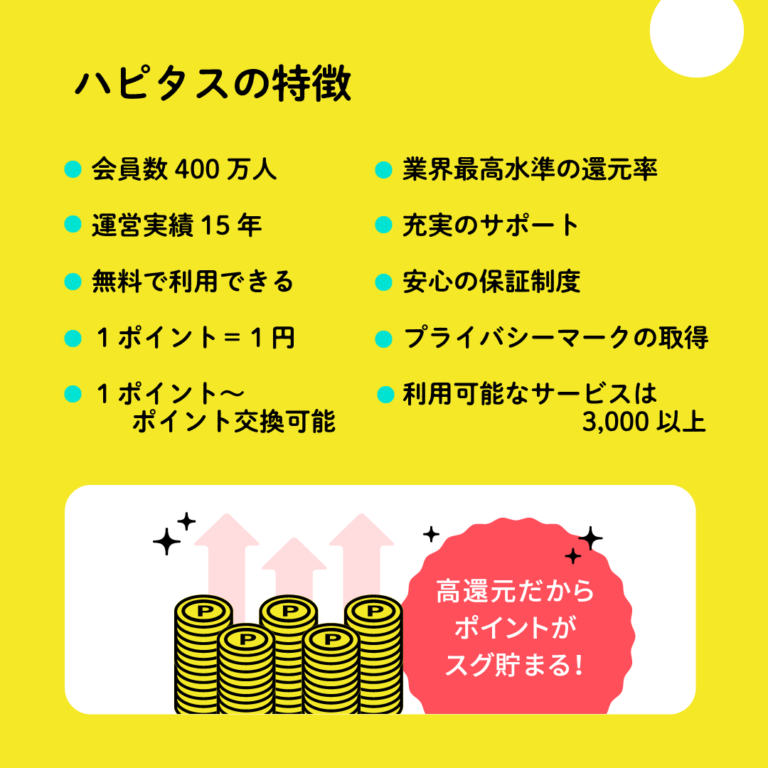5月といえばゴールデンウィークですが、ゴールデンウィークには「こどもの日」があります。
「こどもの日といえば鯉のぼり!」と連想する人も多いですよね。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]私の実家でも昔はこどもの日が近づくと庭に大きな鯉のぼりをあげていましたよ。それもいつの間にかやらなくなりましたが…(笑)[/voice]でもなぜこどもの日に鯉のぼりをあげるのでしょうか?
今回は鯉のぼりをあげる意味や由来などをわかりやすく徹底解説していきます!
こどもの日とは?

でも、端午の節句って、男の子がメインのお祭りよね?
— 星崎梨花セリフbot (@Trb_rika__bot) March 10, 2019
日本では端午の節句である5月5日を「こどもの日」と制定しています。
こどもの日には「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」という趣旨があり、一般的には鯉のぼりや鎧兜を飾るなどの風習があります。
女の子の日である「雛祭り」に対し、「こどもの日」は男の子の日というイメージがありますが、実際は子供であれば特に男女は関係ないそうです。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]しかし本来は男の子のための日だったようですね。[/voice]関連記事:ひな祭りの五人囃子、役割は?意味や由来は?全部まとめて徹底解説!
端午の節句とは?

鯉のぼりをあげる意味や由来をより理解してもらうために、まずは「端午の節句」について説明していきます。
「端午」の「端」には「始め・最初」という意味があり、「午の月」は旧暦で5月のことを指します。
つまり「端午」には「5月の最初の午の日」という意味があり、それが徐々に5月5日のことを指すようになったのです。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]ちなみに「午」が5月だというのは十二支を各月に当てはめた場合の呼び名。11月から「子・丑・寅・卯…」と数えていくと「5月が午(うま)」になります。[/voice]そして端午の節句は中国の「端午節」がルーツだと言われています。
「端午節」では当時国民からの人望が厚かった政治家かつ詩人の屈原(くつげん)を偲んで粽(ちまき)を食べたり、無病息災を祈ってよもぎや菖蒲(しょうぶ)で邪気を払ったりしました。
これが日本に伝わり、日本風にアレンジされたのが「端午の節句」というわけです。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]「端午の節句」というネーミング的に日本発祥だと思っていましたが、中国が起源だったとは!知りませんでした。[/voice]
鯉のぼりの由来は?

鯉のぼり飛んでた pic.twitter.com/5XF5U1Mm98
— いかげそ (@hosimo66) March 10, 2019
中国の「端午節」が日本に伝わって現在の「端午の節句」の形になったのは鎌倉時代からだと言われています。
中国の端午節でも使われていた菖蒲の葉の形が刀に似ていることや、尚武(武道を重んじること)に通じることから、端午の節句は武家にとって縁起が良い重要な行事になりました。
それから端午の節句になると武家社会では生まれた男の子の誕生や成長を願う日として玄関先に家紋のついた「幟(のぼり)」を立てる習慣ができ、武家ではない庶民がその武家社会の風習を取り入れてできたのが「鯉のぼり」というわけです。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]『鯉のぼりはどうみても幟(のぼり)っぽい形じゃないのに、なんで鯉「のぼり」なんだろう?』と疑問に思っていましたが、武家が立てていた幟に影響された名前だったんですね。[/voice]
鯉のぼりの意味は?

https://twitter.com/YGW6fuMcXnzjETZ/status/1102206129268973568
鯉のぼりをあげることには男の子の誕生を神様に伝え成長を祈るという意味があります。
また鯉のぼりが「鯉」である理由は鯉が昔から立身出世の象徴とされているからなんです。
「登竜門」という言葉を聞いたことはありますか?
これは立身出世のための関門や人生の岐路となるような試験のことを意味する言葉ですが、この言葉の成り立ちも鯉が関係しています。
簡単にいうと「中国の黄河にある竜門という激流を登った鯉は竜になる」という中国の言い伝えからできた言葉です。
また鯉は清流ではない池や沼などでも生きることができる生命力を持っており、これらの理由から「誕生した男の子が強く立派に育ちますように」という意味を込めて、端午の節句には鯉のぼりを立てるようになったと言われています。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]たしかにこの理由なら鯉は端午の節句にピッタリな魚な気がしますね。[/voice]
鯉のぼりに「お母さん」がいないのはなぜ?

皆さん「こいのぼり」という歌をご存知でしょうか?
「小さい頃に歌ったことがある!」という人も多いと思います。私もその一人です。
この歌の歌詞をもう一度思い出してみると、
やねよりたかい こいのぼり
おおきいまごいは おとうさん
ちいさいひごいは こどもたち
おもしろそうに およいでる
引用:歌ネット
このように、実はこいのぼりの歌には「お母さん」が登場しません。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]ということは、実際の鯉のぼりにもお母さんがいないってこと?なんで?[/voice]まず先述した通り、鯉のぼりの起源は江戸時代。
当時の鯉のぼりとして飾られていたのは「子供」を象徴する黒い真鯉の一匹だけでした。
それから明治時代になると黒い真鯉に加えて赤い緋鯉も飾られるようになり、童謡「こいのぼり」が作られたのもこの時代です。
真鯉と緋鯉、2色セットの鯉のぼりをみて、童謡「こいのぼり」の作詞者が「真鯉はお父さん」「緋鯉は子供たち」と考えたわけですね。
このとき作詞者が「真鯉はお母さん」にしなかった理由には当時、女性の立場が弱かったことが関係していると考えられます。
そんな時代背景から、2匹しかいない鯉のぼりを家族に見立てた場合に、端午の節句の主役である「子供」と一家の主である「お父さん」という設定になるのも頷けますね。
ちなみに現在の鯉のぼりは
- 真鯉(黒)=お父さん
- 緋鯉(赤)=お母さん
- 青い鯉=子供
となっており、お母さん鯉もしっかり仲間入りしていますよ。
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]現在の鯉のぼりにお母さん鯉が仲間入りしたのは男女平等の風潮からでしょうね。[/voice]
鯉のぼりはいつからいつまで飾る?

鯉のぼりの基礎知識がわかったところで、ここから「鯉のぼりはいつからいつまで飾るのか」をご紹介していきます。
鯉のぼりはいつから飾る?
鯉のぼりを飾る時期についてですが、鯉のぼりをいつから飾るかに明確な決まりはありません。
一般的には3月20日頃の春分の日以降から4月下旬あたりに飾るのが良いとされています。
また4月4日(又は5日)の「清明」の日や、縁起の良い大安の日を選んで飾るのも良いでしょう。
[box class=”blue_box” title=”「清明(せいめい)」とは”]「清明」とは二十四節気の一つで「すべてが清らかで、けがれがない縁起の良い日」という意味で、中国のお盆のような日のこと。[/box]
鯉のぼりはいつまで飾る?
鯉のぼりをしまう時期にも特に決まりはありませんが、あまり長い間飾りっぱなしにしておくと梅雨の時期に入ってしまいますので注意が必要です。
そのことを考えると5月5日の端午の節句が終わった後の天気の良い日に片付けるとカビが発生しづらくて良いかもしれませんね。
また「清明」の日のように、縁起の良い日を選ぶのだとすれば、5月21日頃の「小満」までの大安の日に片付けるが良さそうです。
[box class=”green_box” title=”「小満(しょうまん)」とは”]「小満」とは二十四節気の一つで「すべてのものが成長した頃」という意味がある。[/box] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/eiron1.png” name=”筆者” type=”l icon_black/icon_blue/icon_yellow/icon_red”]個人的には、特に決まりがないのであればGWに入った頃に飾って、GWが終わる頃に片付ければいいかなぁ~と思いました。その方が覚えやすいですし![/voice]
まとめ

今回は鯉のぼりをあげる意味や由来を解説しました。
- 鯉のぼりをあげるのは「こどもの日」だからではなく「端午の節句」だから
- 「端午の節句」は「五月の始め」と言う意味で、無病息災を願う中国の「端午節」という行事が起源
- 鯉のぼりは武家が男の子の誕生や成長を願って玄関先に立てていた家紋の入った幟(のぼり)を庶民が真似たのが由来
- 鯉のぼりが鯉である理由は昔から鯉が立身出世の象徴とされていたから
- 鯉のぼりにお母さんがいないのは作詞された当時の男尊女卑の時代背景が理由
- 現在の鯉のぼりは「真鯉(黒)=お父さん」「緋鯉(赤)=お母さん」「青い鯉=子供」という形
- 鯉のぼりを飾る時期に明確な決まりはないが、3月20日頃の春分の日から4月下旬までに飾り、5月21日頃の小満の日までにしまうのが一般的
普段何気なくやっていた端午の節句などの行事も、掘り下げて調べてみると色々な由来や意味が隠れていることがわかりました。
現在ではこどもの日に男女関係はないそうですが、由来や意味を知るだけで実際に行事を行うときの心持ちが変わる気がしますよね。
この機会に他の行事の意味や由来を調べてみても面白いかもしれません。