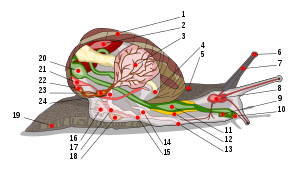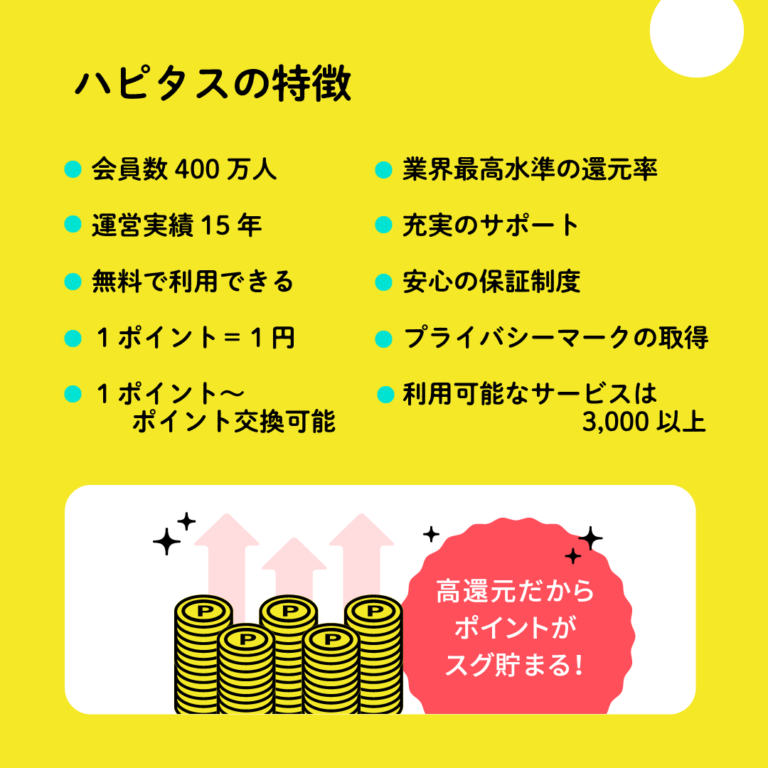葉物野菜が美味しい季節。
直売所で買ったりした時に、こんなことありませんか?
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]お母さん、見てみて!レタスの中にカタツムリがいたよ![/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]え~!わぁ、本当だ。小っちゃいね。[/voice] [voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]ねえ、カタツムリって、生まれた時から殻があるの?取れたらナメクジになるの?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]え…。う~ん、どうだろう?[/voice]子供の小さな疑問に、タジタジですよね。
ここでは、そんなカタツムリのいろいろをご紹介します。
お子さんと一緒に、カタツムリの謎を解き明かしていきましょう。
カタツムリの殻の謎
カタツムリの殻には、どんな秘密があるのか?ご紹介していきましょう。
カタツムリはいつから殻をつけているの?
答えは、「生まれた時から」です。
カタツムリの殻は体の一部で、大事な内臓が収まっています。
殻を取ったらナメクジになる、ということはありません。
カタツムリの殻は何でできているの?
カタツムリの殻は、体と一緒に成長していきます。その成分は主に炭酸カルシウムです。
よく雨の日に、濡れたコンクリートに集まるカタツムリを見たことはありませんか?
あれは、濡れたコンクリートから炭酸カルシウムが溶け出しているから。
それを舐めに集まってきているのです。

コンクリートがない場合には、カルシウムを含む石やサンゴ、死んだ仲間の殻などから摂取します。
カタツムリの殻は、割れても再生します。
体が傷ついた時と同じで、ゆっくりと補修されていきます。
けれども内臓まで傷ついてしまうと、死んでしまうこともあります。
特に赤ちゃんカタツムリは、殻が丈夫ではないので優しくしましょう。
殻はどんな風に大きくなるの?
生まれたばかりのカタツムリは、体長約2㎜。米粒くらいの小さい姿です。
でも、自力で土の中から這い出して来るのです。たくましいですね。
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=3DN0KVRVdDM” /]成長はゆっくりで、1か月で体長約3㎜。
殻は、入り口からだんだんと巻いていって、大きくなります。
また、内側も厚みを増して大きくなります。
生まれたばかりの殻は、1周り半くらいですが、大きくなると3~4周りほど巻いています。
また、大人のカタツムリだと、殻の入り口が反りあがってきます。

どのくらいの大きさになるかは種類によって違います。
日本の固有種では、1㎜前後の小さな種類から、数㎝までいろいろです。
一番大型のカタツムリは四国の「アワマイマイ」で殻の直径が6㎝まで大きくなります。
また、アフリカには殻が20㎝、体長が40㎝になる巨大なカタツムリも生息しています。
なぜカタツムリは殻をもっているの?
カタツムリの祖先は、もともと水の中で暮らしていた貝の仲間でした。
それが、水から陸に上がるときに、陸地の環境に慣れるために体を進化させていったのです。
進化がさらに進み、殻をなくしたのが「ナメクジ」と考えられています。
殻は、乾燥から体を守り、急に気候が変わっても耐えられるようになっています。
また、外敵から身を守る役目もあり、眠る時に殻の入り口を閉じて眠ります。
さらに冬眠する時は、入り口を2重3重にして閉じ、寒さと乾燥から身を守っているのです。
カタツムリの殻は右巻き?左巻き?
日本に生息するカタツムリの大部分は「右巻き」です。
遺伝的に巻く方向が決まっています。
左巻きは少数で、「ヒダリマキマイマイ」という種類になります。

巻き方は、殻の渦巻きを上から見て、殻の入り口が右を向いているか、左を向いているかで判断します。
カタツムリの飼い方の謎
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]お母さん、カタツムリを飼ってもいい?[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”l”]…いうと思ったよ。でも、カタツムリってどうやって育てるんだろう?[/voice]

知っているようで、知らないことの多いカタツムリ。
でも、気を付ける点が分かっていると、案外簡単に飼育することができます。
ここからは、長く元気に飼うためのコツをご紹介していきます。
カタツムリは何を食べるの?
カタツムリは雑食ですが、主に柔らかい葉っぱを好みます。
家庭で飼うのであれば、野菜の皮や芯、外側のちょっと痛んだ葉っぱなどで大丈夫。
けれども、赤ちゃんカタツムリの場合には、柔らかい葉っぱでないと食べられません。
芯に近い部分の柔らかい葉を与えてあげましょう。
また、殻が大きく成長するためには、炭酸カルシウムが必須です。
卵の殻、貝殻などをあげます。細かく砕かなくても大丈夫です。
鳥用の「カットルボーン」や爬虫類用の「カルシウムパウダー」でも代用できます。
野菜をあげる時は、農薬が付いている場合があるので、軽く水洗いしてからあげましょう。
アジサイによくいるイメージがですが、アジサイの葉には毒があるので、あげないようにしましょう。
[box class=”pink_box” title=”関連記事”]紫陽花には毒がある?カタツムリに影響は?致死量や症状例は?[/box]
面白いことに、カタツムリは食べ物の好みが、それぞれ違います。
甘い野菜が好きなカタツムリがいれば、そうでないカタツムリもいるので、観察してみましょう。
野菜も卵の殻も、鮮度が落ちると食べてくれません。
できれば、毎日取り換えるようにしましょう。
また、炭酸カルシウムが足りなくなると共食いをしてしまうことも。
何匹か一緒に飼う時には、気を付けましょう。
どんな入れ物に入れればいい?
蓋がきちんとできて、空気が通るものであれば、何でも大丈夫です。
ただし、ダンボールなど湿気を吸って変形するものなどは向きません。
昆虫用の飼育ケースなど100均で売っているもので大丈夫です。
生野菜を入れるので、コバエが心配な方は、コバエが侵入しないタイプの飼育ケースをお勧めします。
飼育ケースの中は何を入れればいい?
赤ちゃんカタツムリと大人のカタツムリでは、入れるものが少し違ってきます。
[box class=”green_box” title=”底にひくもの”]①濡らしたティッシュペーパー、キッチンペーパーまたはタオル赤ちゃんカタツムリを飼う時におすすめ。
土と違って、白いので見分けがつきやすいですし、取り換えも簡単です。
大人のカタツムリを飼う時にも使えます。
②川砂・腐葉土
大人のカタツムリを複数飼うときに入れましょう。
卵を産むときには、土が必要になります。
腐葉土にカビが生えないように時々日光消毒をしましょう。[/box]
[box class=”green_box” title=”そのほかに入れておくとよいもの”]① エサ皿
用意しておくと、エサの取り換えが楽になります。
② 木の枝や石など
高低差をつけると、カタツムリが上ったり下りたりする様子が観察できます。
カタツムリも自然に近い環境でストレスが減ります。[/box]
ケースはどこに置くのがいい?
日陰の風通しの良いところがおすすめ。
カタツムリの適温は20℃前後です。
暑すぎても寒すぎても、殻の入り口を閉じてしまいます。
また、乾燥は厳禁。
1日1回、乾燥がひどい時には2回、霧吹きで水を撒いてあげましょう。
冬場になると、気温が下がり、5度以下になると冬眠します。
腐葉土や木の枝などを多くして、1日1回霧吹きで水を撒いてあげましょう。

もしも、20℃で保たれる場所に置いていれば、冬眠はしません。
その場合も霧吹きで水を毎日あげましょう。
寿命はどのくらい?
2~3年くらいですが、記録では15年生きたものもいるそうです。
種類によって、寿命はだいぶ違いますし、飼育環境でも大きく違ってきます。
カタツムリはどうやって生まれるの?
カタツムリは雌雄同体。オスメスの区別がありません。
2匹以上いれば、交尾をして卵を産みます。
5月~8月に産卵。1回に20~30個ほどの卵を産みます。
卵は1か月ほどで孵化して、赤ちゃんカタツムリが地上に出てくるのです。
生まれて1年ほどで大人になりますが、目安は、殻の入り口が反っているかどうかです。
カタツムリの危険な謎
[voice icon=”https://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2019/02/娘普通.png” name=”娘” type=”r”]あっ、キャベツ食べてる!かたつむりって、可愛いね~。[/voice] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”l”]そうだね。でも触ったら必ず手を洗ってね。危険な虫がついていることもあるんだよ。[/voice]
カタツムリは、寄生虫に侵されていることがあります。
気を付けないと、人間にもうつることがあるのです。
ロイコクロリディウム
成虫は鳥の腸に寄生していて、その卵が糞と一緒に出てきます。
それをカタツムリが食べると、体内で孵化し、脳を操って次の宿主である、鳥を誘います。
寄生されたカタツムリを食べてしまうことで、人間にもうつることが心配されます。
主にヨーロッパが生息地ですが、近年北海道で見つかった例もあります。
広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう)
主にネズミなどに寄生していますが、その糞を食べたカタツムリやナメクジにも寄生します。
人間に感染すると、2週間ほどしてからインフルエンザに似た症状を発症し、髄膜炎を起こします。
アフリカマイマイに寄生することが多く、東南アジア・沖縄・小笠原・奄美大島などに生息しています。

野生のカタツムリを食べて寄生されてしまったケースが報告されています。
食用のアフリカマイマイは寄生されないように、厳重に管理しているので心配ありません。
いずれもカタツムリの種類が限定されていたり、海外だったりしますが、注意は必要です。
死に至る病気ではなくても、雑菌などの心配もあります。
カタツムリに触ったら、必ず手を洗いましょう。

まとめ
カタツムリの殻の謎や赤ちゃんカタツムリの成長、お家での飼い方を紹介しました。
- カタツムリは生まれた時から殻をもっていて、成長とともに大きくなります。
- カタツムリをお家で飼う時には、野菜と炭酸カルシウムをあげて、霧吹きで水をあげましょう。
- 危険な寄生虫を持っていることもあります。触ったら忘れずに手を洗いましょう。
カタツムリののんびりと這う姿は、せかせかした気持ちを癒してくれます。
いろいろな謎を解き明かしながら、お子さんと一緒に、夏休みの研究にしてもいいかもしれませんね。
[box class=”pink_box” title=”関連記事まとめ”]・カタツムリの漢字の由来と語源!そのほかの呼び方とは?!