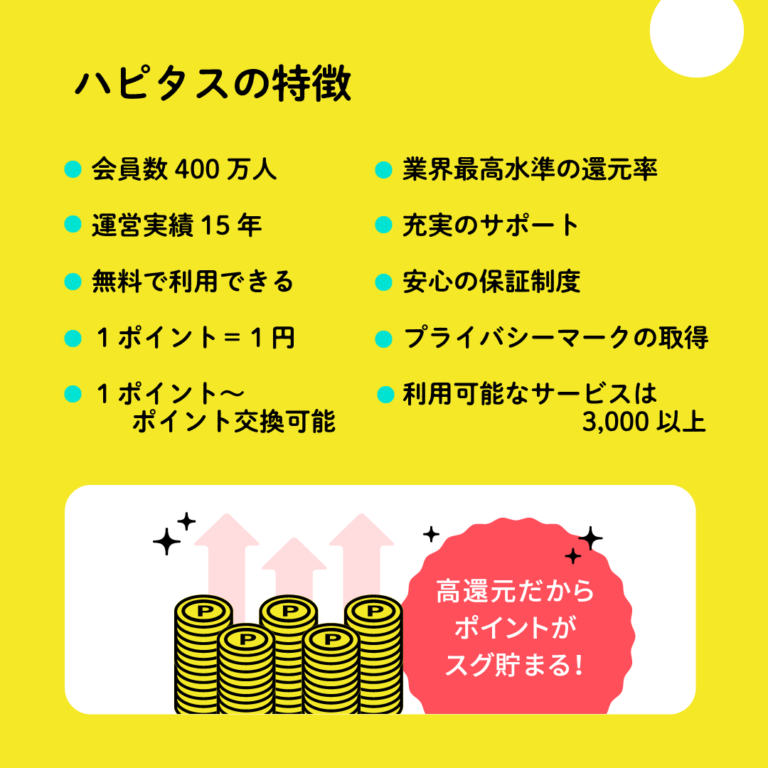皆さん、衣替えはいつ行いますか?
だんだんと過ごしやすくなり、日の長さも変わってきて次の季節の気配を感じると着るものも変わってきます。
季節の変わり目って何を着て良いか困りませんか?
私は去年も同じ季節を過ごしているはずなのに、なぜか着るものがない・・・何を着ていたっけ?と毎年迷っている気がします。
今回は皆さんも行う衣替え、いつ行えばいいのか、そもそも何月に定められているのか、ちょうどいいタイミングをお伝えします。
また、衣替えの注意点もお教えするのでチェックしてみてくださいね。
衣替えのタイミング
衣替えは何月に行うもの?
季節によって服装を変える衣替え、地域によって時期に違いがありますが行う日が決まっています。

ほとんどの地域は
- 春服⇒夏服が6月1日
- 秋服⇒冬服が10月1日
に衣替えが行われます。
ただ、北海道のような寒い地域や逆に沖縄のように暑い地域は、他の地域と気温が違うので衣替えの日も変わります。
北海道などの寒い地域は
- 春服⇒夏服は6月15日
- 秋服⇒冬服は9月15日
と、気温が低い月が長いので夏服になるのが遅く、冬服になるのが早い傾向にあります。
沖縄などの暑い地域は
- 春服⇒夏服は5月1日
- 秋服⇒冬服は11月1日
と、寒い地域とは逆に夏服になるのが早く、冬服になるのが遅くなります。
気温が全然違っているので、ほとんどの地域と同じタイミングで衣替えを行ったら大変なことになってしまいますからね。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]学校の制服や会社で働く皆さんのスーツや服装もこの日に合わせて変わりますよね。着るものが変わると気分まで変わってきますよね。服で四季を感じるのもいいものですよね。
[/voice]衣替えのタイミング、気温では?
その地域ごとに日にちが決まっている衣替え。
とはいえ、まだまだ暑い日があったり、肌寒い日があったりと、衣替えの日が来たから完全に服装を変えるのは出来ませんよね?
やはり衣替えのタイミングで大事になってくるのは気温、特に最高気温です。
ここでは東京の季節ごとの最高気温と合う服装をご紹介します。
[box class=”pink_box” title=春(3月~5月):15℃~25℃]
軽めのジャケットや薄手のニット、5月になれば半袖で過ごせます。朝・夜と日中との気温差が大きいこともあるので羽織れるものがあると便利です。[/box]
[box class=”yellow_box” title=夏(6月~8月):25℃~32℃]
薄手のもの、半袖、Tシャツやノースリーブなどで過ごせます。6月~7月の梅雨時期は気温が下がり寒くなることもあるので羽織れるものがあると便利です。
梅雨が明け、本格的な夏になると夜でも25℃を超えたままの熱帯夜や、最近では最高気温が35℃位になったりと非常に暑いので風通しの良い服装がおすすめです。[/box]
[box class=”green_box” title=秋(9月~11月):27℃~17℃]
9月は真夏程ではないものの、日中は暑い日が続きます。半袖や薄手の服で過ごせます。10月からは過ごしやすくなるので春と同じような薄手のジャケットやニットなどが必要になってきます。[/box]
[box class=”blue_box” title=冬(12月~2月):12℃~10℃]
コート、厚手のニットやジャケットが必要です。1月の終わりから2月ごろは東京でも一桁台の気温の日があります。足元から冷えるのでブーツも必要です。
インナーも暖かいものがあるので寒がりの方は重ね着が必須ですね。[/box] [voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]人によって気温の感じ方が違うので、あくまでも目安にしてくださいね。
夏は冷房が強くて寒い場所もあるので特に女性は薄い羽織物が欠かせない!という方もいらっしゃいますよね。[/voice]
衣替えの風習はいつからあるの?
時期が来れば当たり前のように衣替えを行うこの風習。
一体、いつからあるのでしょうか?
平安時代の衣替え
実は元々中国の風習でした。それが平安時代に日本へ伝わり宮中行事として根付きます。
平安時代は衣替えのことを更衣(こうい)と言っていました。
しかし、天皇の着替えの役目を持つ女官の職名も同じく更衣(こうい)と言うため、区別をするために民間で言い方が変わり衣替えと言うようになりました。
更衣(衣替え)の時期は
- 旧暦4月1日は冬装束から夏装束
- 旧暦10月1日は夏装束から冬装束
着物だけでなく、手に持つ扇も冬は桧扇(ひおうぎ)というヒノキ製のもの、夏は蝙蝠(かわほり)という紙と竹製のものと決められていました。
江戸時代の衣替え
江戸時代になると江戸幕府は年4回の衣替えの日とそれに合わせた着物を制度化しました。
[box class=”pink_box” title=”衣替えの日と着物”]- 旧暦4月1日 ~5月4日は袷(あわせ)
袷:裏地付きの着物
- 旧暦5月5日~8月末日は単衣(ひとえ)、帷子(かたびら)
単衣:裏地の無い一枚の着物
帷子:生糸・麻で仕立てられた着物
- 旧暦9月1日~9月8日は袷
- 旧暦9月9日~翌年3月末日は綿入れ
綿入れ:表布と裏布の間に綿を入れた着物
[/box]と定められていました。
この江戸時代に庶民にも衣替えが浸透しました。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]江戸時代はこんなにもしっかり日付と着るものまで決められていたんですね。[/voice]明治時代以降の衣替え
明治時代になり、和服から洋服へと変わります。
明治政府は役人・軍人・警察官の制服を洋服に定めました。
明治6年(1873年)1月1日から今使われている新暦が施行されたため、衣替えの時期もそれに合わせ変わります。
新暦6月1日~9月30日が夏服
新暦10月1日から翌年5月31日が冬服
と定められました。
これが官公庁・企業・学校など一般の人にも定着し、毎年6月1日と10月1日に衣替えを行うようになりました。
衣替えで整理整頓
昔からの風習の衣替えですが、いざやろう!となるとちょっと面倒だったりしますよね。
でも、せっかくやるのならただ服を入れ替えるだけでなく整理整頓もしちゃいましょう。
[box class=”pink_box” title=整理整頓のポイント]- これからも着るもの、3年位着ていないものに分ける。
- 色褪せやシミなどがないか見る。
- サイズは合うか、形は崩れていないか確認する。
- 毛玉やヨレ、衣服の伸びはないか見る。
- これからも着たいものかどうか
よく、3年着なかったものはもう着ないとも言われますよね。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]サイズは大丈夫でも着てみるとちょっと野暮ったいシルエットになってしまったり、昔は気に入って買ったものが、いつの間にか似合わなくなっていることもあるので鏡の前でいろいろ見てみましょう。[/voice]残す・捨てる・迷うBOXをそれぞれ用意して仕分けすると散らかることもなく、分かりやすく分類できるのでおすすめです。

また、着ない洋服でもきれいなものはリサイクル店に出せば無駄にもなりませんよ。
衣替えの注意点
これから着る洋服の準備が出来たら今まで着た服の収納もしっかり行いましょう。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]きちんと保管しておかないと、次に着ようと思ったときに見覚えのないシミが出来てしまったり、お気に入りの服が虫食いで着れなくなってしまった!なんてショックなこともあるので気を付けましょう。[/voice] [box class=”pink_box” title=衣替えの注意点]- クローゼット・収納ケースをきれいに掃除する。
一度服を取り出したら、また収納する前に収納場所をきれいにしましょう。
クローゼットや収納ケースには衣類から出たほこりがいつの間にか溜まっています。そのまましまっては大事な洋服の汚れの原因に!しっかり取り除きましょう。
- 洗ってから収納する。
収納する前には必ず洗いましょう。
目に見えない汚れが落ちていないまま収納すると、次に着るときにシミや黄ばみの原因になってしまいます。しっかり洗いましょう。
- 衣替えは晴れている日に!
収納するときに気を付けたいのは湿気です。
湿気が残ったまま収納するとカビの原因に。
洗った洋服をしっかり乾かすのはもちろん、クローゼットや収納ケースも風を通したり除湿器を使って湿気を取りましょう。
- 大事な洋服や汚れが落としづらいものはクリーニングへ
家で洗濯しづらい素材や大切な洋服はクリーニングに出しましょう。
また、クリーニングから戻って来たときにかけてもらっているビニールは必ず外しましょう。意外とつけたまま収納している方も多いかと思います。
ビニールは湿気がこもってしまい、カビの原因に。
ほこりが付かないようにしたい場合は不織布などの通気性の良いカバーに入れ替えて収納しましょう。
- 防虫対策は忘れずに
お気に入りの衣類が虫食いで着れなくなった!なんてショックな出来事を防ぐためにも防虫剤は必ず入れておきましょう。
引き出しにしまう時は衣類の間や下に置いては効果は半減です。防虫剤は空気より重いので衣類の一番上に置きましょう。一緒に除湿剤もあればなお、安心ですよ。
[/box]
この投稿をInstagramで見る
まとめ
今では当たり前のように行っている衣替えが、実は平安時代に中国から伝わってきた風習だったとは知らなかった方も多いのではないでしょうか?
四季がある日本だからこそ、その季節ごとに装いを変えて楽しめますよね。

今回の衣替えについてのレポートをまとめてみましたのでチェックしてみてください。
[box class=”pink_box” title=まとめ]- 衣替えは日にちが決まっていて大体の地域では春服
⇒夏服が6月1日、秋服⇒冬服が10月1日
- 寒い地域や暑い地域は日にちが違う
- 衣替えは平安時代に中国から渡ってきて、江戸時代に庶民にも根付いた
- 現在の衣替えの日にちが定められたのは明治時代
- 衣替えにあわせて整理整頓を行う際にはしっかり仕分けする
- 収納の際には収納ケースも隅々まで掃除し、湿気も取り除くこと
せっかく気に入って買った衣類、収納するものも処分するものもしっかり「ありがとう」の気持ちを込めましょうね。
[box class=”pink_box” title=関連記事]衣替えで押さえておきたい収納のコツ!合わせて覚えたい衣替えで必要な正しい洗濯法!
[/box]