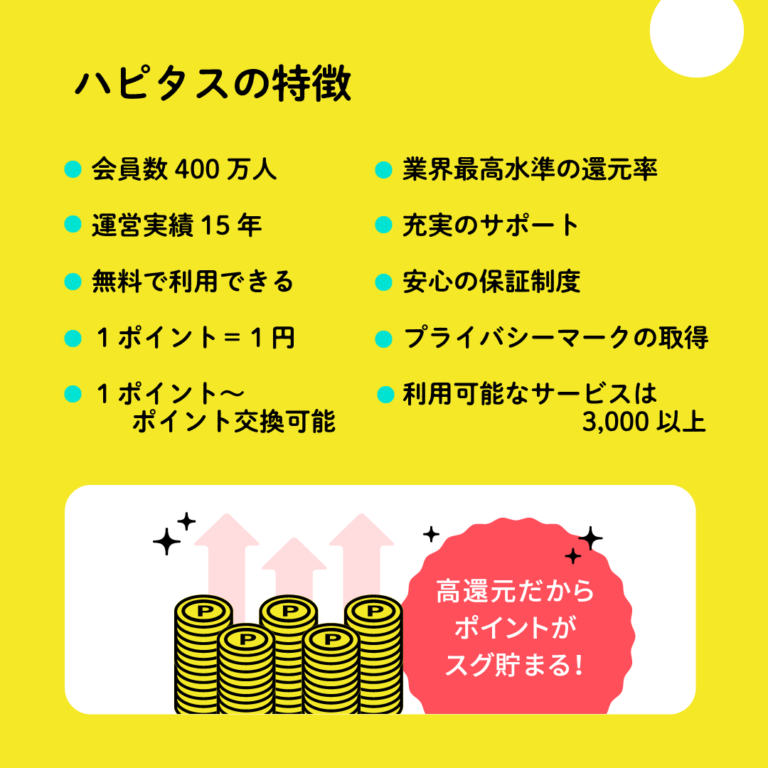2月になるとすぐにやってくるのが節分。私が幼い頃は次の日に鳥が豆をつつきにきていたものです。
ところで皆さん節分についてどれくらいご存知ですか?今日は豆まきをする時間や正しい方法などをご紹介したいと思います。
節分ってなに?
節分とは立春の前日のことです。元々は季節の分かれ目のことでした。季節の変わり目には邪気が入りやすいとされ、新たな1年の前に様々な行事が行われていました。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]昔は冬から春になるのを新たな1年としていたのよ[/voice]今では1年の邪気を払い、新年の無病息災を願って豆まきなどを行ないます。
元々節分は季節の分かれ目ということで4回(立春、立夏、立秋、立冬)ありました。しかし江戸時代ごろになると節分=立春という考えが定着しました。
なぜ豆を撒くの?
節分と切っても切れないのが豆まきですよね。それにしてもなぜわざわざ豆を撒くのでしょうか。
その起源は平安時代にまでさかのぼります。平安時代の宮中では追儺(ついな)という邪気払いの中に豆打ちという行事があり、その豆打ちだけが庶民に広がりました。

また豆には穀物の精霊が宿っているとして神聖なものとして見られていました。そのため神事にもよく使われていました。
ほかにも豆は「魔滅」(魔を滅する)と書くことができるため豆を撒くと鬼を追い払うことができるとされています。
鬼が出たときに毘沙門天(びしゃもんてん:仏教における仏神。武神)のお告げで豆を撒くと鬼を退治できたという逸話もあります。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]豆を撒くことになったのにはいろんな理由があったのね[/voice]
豆まきをする時間ってあるの?
豆まきは一体どの時間帯に行なえばいいのでしょうか。実は豆まきは夜に行なうのがいいとされています。1番いい時間帯はなんと深夜の1時から3時にかけてと言われています。

なぜなら鬼がやってくるのは夜、しかも丑三つ時。つまり深夜1時から3時からです。しかしそんな時間に豆まきをするのは現実的ではありませんね。
そのため今では夜にするのが正しいとされています。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-9.png” name=”かな” type=”r”]鬼が来るのが夜だなんて子どもたちが知ったら寝られなくなっちゃうかもしれないなあ。黙っておこうっと[/voice]
正しい豆まきのやり方
実は豆まきには正しいやり方があるのはご存知でしょうか。
用意
まずは用意するものから。福豆と呼ばれる煎り豆、もしくは殻付きの落花生を使います。福豆は神棚に備えておきましょう。神棚がない場合は盛り塩と一緒に供えるといいです。
一般的には福豆が使われますが、北海道、東北、鹿児島県、宮崎県では落花生が使われます。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]芽が出ない、散らばらない、雪の中で拾いやすい、拾って食べるのに抵抗がないといった理由で使われているのよ[/voice]ちなみに鹿児島県や宮崎県の場合は落花生の産地があるからだと言われています。

そしてなぜ煎り豆が使われるのか。それは生の豆だと拾いきれなかったときに芽が出てしまうからです。拾い忘れた豆から目が出ると縁起が悪いとされています。
理由は豆=魔(物)から芽が出てくるという意味になってしまうからです。

また煎る=射るとして縁起がいいからとも言われています。
豆を撒く人
実は豆を撒く人はその家の主人と決まっています。もしくは年男、年女、厄年の人が撒くと縁起がいいとされています。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]でも今はそれほど気にしなくって大丈夫よ[/voice]豆の撒き方
まずは基本的なことから。「鬼は外」の掛け声で部屋から外、もしくは玄関のほうに向かって豆を投げます。「福は内」の掛け声で部屋に向かって豆を投げます。
そしてこれらの作業を各2回ずつ行なって部屋の奥から玄関まで向かいます。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]鬼という字がつく地域では「鬼は内、福も内」という場合もあるそうよ[/voice]豆を撒き終わったら年齢+1の数の豆を食べます。なぜ1つ足すのかというと、来年の健康であることを願うという意味があるからです。
なぜ来年なのかというと、昔の新年の数え方は立春が始まりだったからなのです。そのため節分は大晦日のように考えられていました。
つまり新年の前日に節分を行い、来年のために願いをこめる形で1粒が加わりました。
[voice icon=”http://yosiaa.com/wp/wp-content/uploads/2018/10/nigaoemaker-6.png” name=”かな” type=”r”]でも満年齢の数を食べるのが間違いっていうわけでもないのよ[/voice]
豆まき以外の風習
節分には豆まき以外にも様々な風習があります。
柊鰯(ひいらぎいわし)
柊の枝に鰯の頭を刺して玄関に飾ります。鰯を焼く匂いで鬼は近づけず、柊で鬼の目を刺すので、家には入れないとされています。
節分鰯、焼嗅(やいかがし)、やっかがし、いわしひいらぎなどとも呼ばれています。
昔から尖ったものや臭いものには魔除けの効果があるとされていました。
柊鰯は節分から立春まで飾るのが一般的です。
処分の仕方は神社に持って行くのが最良ですが、半紙に包み塩で清めてから捨てても大丈夫です。
恵方巻
こちらはとてもなじみ深い行事だと思います。
恵方巻はその年の年神様がいる方向を向いて巻きずしを食べ、福を願う行事です。
このときに言葉を発せずに最後まで一気に食べると願い事が叶うとされています。幸運巻きずし、恵方ずし、招福巻とも呼ばれるそうです。
この投稿をInstagramで見る
1990年代後半から認知度が上がりました。
それは1989年に広島のセブンイレブンのある店舗が、大阪には節分に太巻きを食べるという話を聞いて仕掛けたことがきっかけとなったからです。
恵方巻の起源は江戸時代後半に大阪の商人が商売繁盛を願って始められたとも、大正時代に花街でふるまわれたことをきっかけに始まったとも言われています。
こんにゃく
四国地方などでは節分にこんにゃくを食べる風習があります。
こんにゃくは食物繊維が豊富で食べると体のいらないものや毒素を出してくれるので、昔の人たちは「胃のほうき」と呼んでいました。
大掃除のあとや大晦日、節分にはこんにゃくを食べて体内をきれいにします。
そのほかにもけんちん汁やそばを食べる地域もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
[aside]こちらもどうぞ節分の食べ物は関西と関東ではどう違うの?食べ物の意味も解説! [/aside]
まとめ
豆まきにも正しいやり方があるのは驚きでした。けれど今はそれほど気にせずに、家族みんなが楽しくできればいいと思います。
[box class=”pink_box” title=”節分の正しいやり方”]- 豆は夜に撒く
- 家長もしくは年男、年女、厄年の人が撒く
- 奥の部屋から2回ずつ撒いていく
- 健康を願って年齢+1の豆を食べる[/box]
節分に来るのは赤鬼だけ?鬼はなぜ色んな色をしているの?その意味とは
春分の日の由来は?いつ?何する日?これを見れば全て分かります!
冬の雑学まとめ[/box]